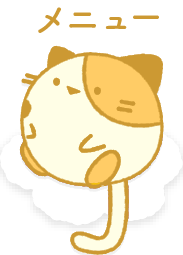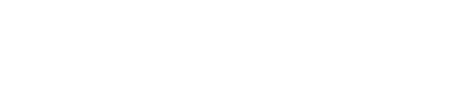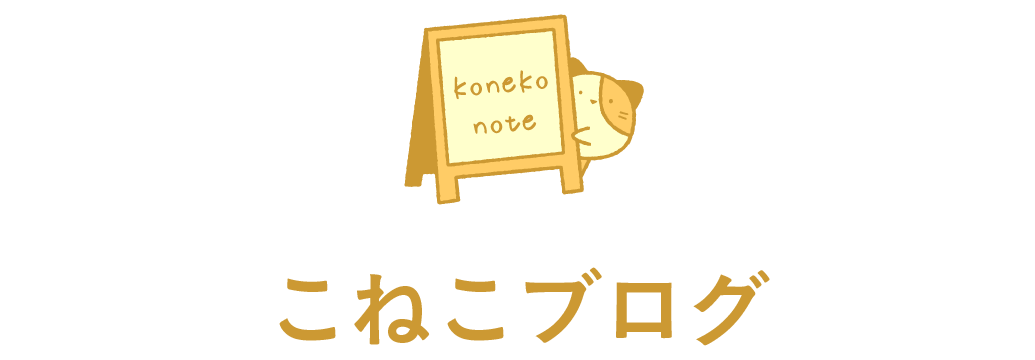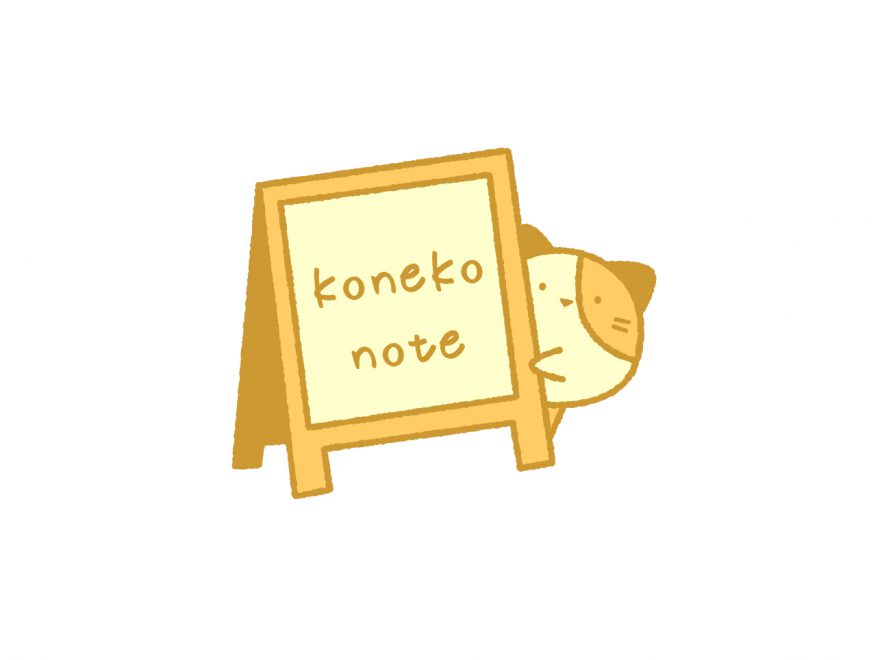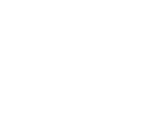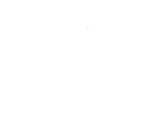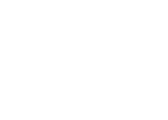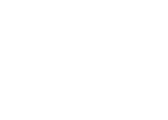─────────────────────────────────────────
このページでは、毎月スタッフ向けに発信している内容を、皆さまにもご紹介しています。
─────────────────────────────────────────
こんにちは、野口です。
今月は、今年度上期の職員の人事考課面談が終わりましたので、その振り返りを含めてお話をしました。
テーマは「問題が起きたときの対応方法」と「日々の学び方」についてです。
まず大前提として
ここでお話しするのは“日々の仕事の中で起きる一般的な問題や課題”についてです。
いわゆる不適切保育のような重大な事案は別の問題であり、今回の内容とは切り離して考えていただければと思います。
問題が起きたときの考え方
仕事をしているなかで、問題が起きるということは当たり前です。
課題があって当たり前なので、問題がなぜ起きたかではなく、
どう対応したか、どう再発を防げる仕組みを作ったかという点が非常に重要です。
問題が起きたからといって評価が下がるのではなく、取った対応こそが評価されます。
そして特に気をつけたいのは、「人のせいにしないこと」です。
誰かのせいにしても問題は解決しませんし、逆に評価も下がります。
私たちが大切にしているのは、
前向きに受け止めて、再発防止の仕組みを一緒に考えてくれる姿勢です。
問題が起きたからといって「この園はダメだ」と思う必要は一切ありません。
一人ひとりがどう受け止め、どう対応し、どう再発防止を仕組みにしていくか。
そして、「もう二度と起こさない」と考えられるかが大切です。
こうした取り組みの積み重ねによって園は強くなり、その努力が評価されていきます。
これが、今回の上半期の振り返りです。
学び方について
併せて、問題が起きたときに「どう学んでいくか」も大切です。
科学的に見ると、非効率な勉強方法として証明されているものがあります。
・テキストをただ読む
・下線やハイライトを引くだけ
・ノートをきれいにまとめる
これらは大人の学び方としては効果が低いとされています。
一方で、効率的な勉強方法は次の通りです。
・シミュレーションを行う
・間隔(期間)を空けて繰り返し練習する
・質問形式でメモをする
分からないことがあったら、ただ書き留めるのではなく、
質問形式を通して理解を深めることを意識していきたいと思います。
まとめ
今回の話をまとめると
仕事上の問題は「どう対応するか」で評価が決まる
学び方においても「次に起こさない工夫」と「質問形式を活用した理解」が大切
こうした積み重ねを通じて、次の半年をより良いものにしていければと思います。