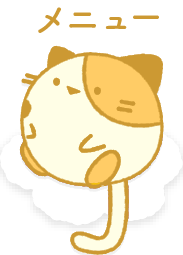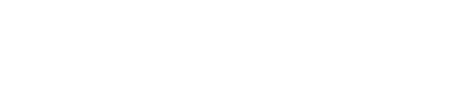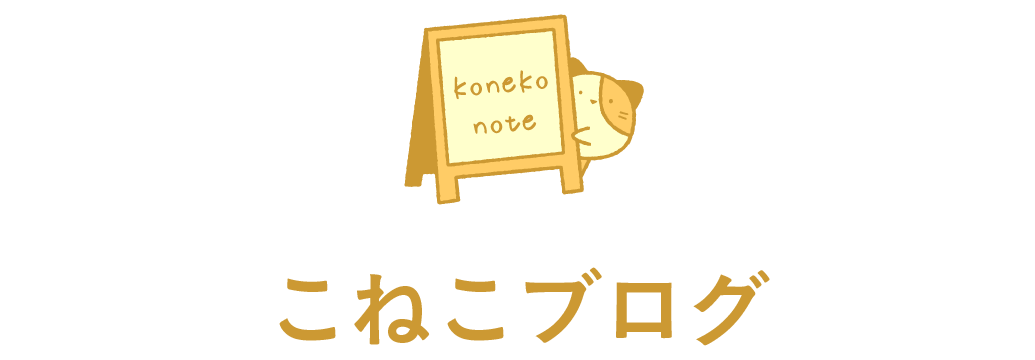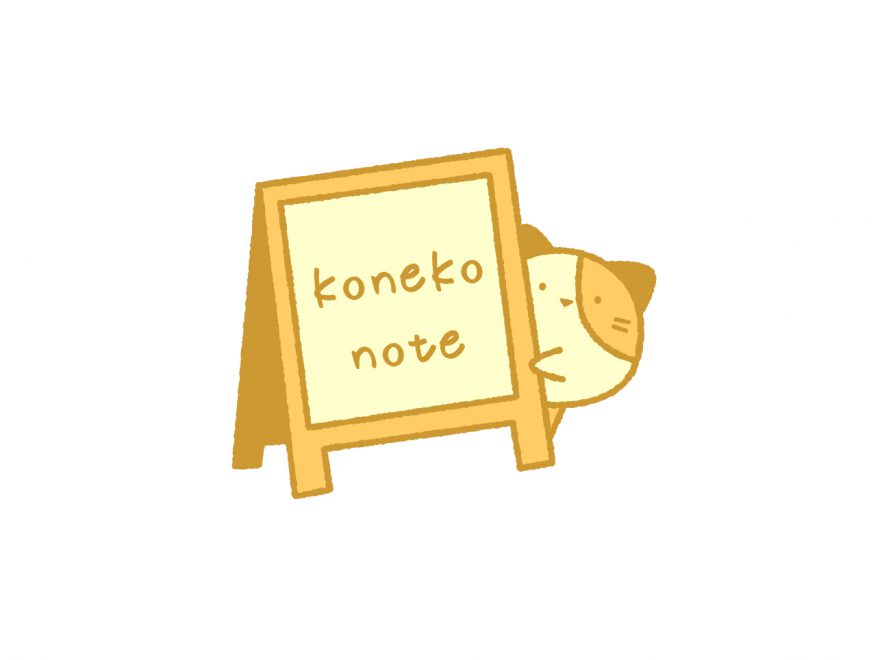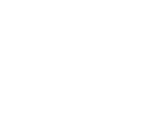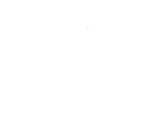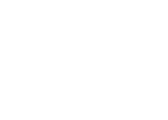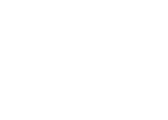─────────────────────────────────────────
このページでは、毎月スタッフ向けに発信している内容を、皆さまにもご紹介しています。
─────────────────────────────────────────
こんにちは、専務の野口です。
今回、8月の全体会議でお話ししたテーマは、大きく2つあります。
「問題解決の姿勢」
「愛着関係と探索活動」
この2つについて、日々の保育の中でも意識していただけたらと思い、お伝えしました。
◆ 問題解決について-誰かを待つのではなく、自分から動くということ
保育の現場では、日々いろいろな出来事が起こります。
その中で、「こうすればもっと良くなるのでは」と感じることもあれば、「ちょっと気になるな」と思うこともあります。
そうした時、
●問題だけを報告する人
●問題を相談として持ってくる人
●自分の考えを添えて伝えてくれる人
それぞれの姿勢があります。
「問題だけを持ってくる人は、誰かに解決してもらうのを待っている」状態です。
やはり「こうしたら良くなるかもしれません」と自分なりの視点やアイデアを持って動こうとする姿勢は、周囲からの信頼にもつながります。
問題を見つけたとき、最初の一歩を踏み出す勇気、そして周囲を巻き込みながら改善していく行動力。
それらを持つ職員には、自然と信頼やチャンスが集まってくると感じています。
また、強いチームには「信頼できる仲間」の存在があります。
・自分が良くないときに、きちんと指摘してくれる優しさがある人。
・苦しいときに、まず“味方”でいてくれる人。
そんな仲間がそばにいることで、安心して挑戦し続けられる環境が生まれます。
こねこのーと保育園では、園ごとにそうした“信頼で結ばれたチーム”をつくっていきたいと考えています。
◆ 愛着関係と探索活動
2つ目のテーマは、「愛着関係(アタッチメント)と探索活動」についてです。
アタッチメントとは、子どもが恐れや不安を感じたときに、特定の信頼できる大人にくっつくことで安心し、気持ちを落ち着けようとすることです。
たとえば、怖くて不安でしかたがないときに、「この先生がそばにいれば大丈夫」と感じられるようになる――この安心感が、まさに“愛着関係”です。
このような絶対的な安心感が育っているからこそ、子どもたちは新しい遊びや場所に対して、自分から一歩を踏み出して挑戦すること(探索活動)ができるようになります。
遠藤俊彦先生のアタッチメントの著書にも、「アタッチメントと探索活動は表裏一体である」と書かれています。
私たちが日々の保育の中で大切にしている姿勢や関わりも、この考え方につながっています。
たとえば…
・なぜ絵本を一緒にあまり読まないのか
・なぜ抱っこをあまりしないのか
こうした一つひとつの行動の背景には、愛着関係や育児担当制の考え方が深く関わっているのです。
「これはやらない方がいいよね」となった場面で、
単に“ダメと言われたから”ではなく、
なぜそうなのか?
愛着や育児担当制の視点ではどう捉えられているのか?
という問いを持ち、考えてみてほしいと思います。
実はその答えやヒントは、すでにたくさんの本の中に書かれていて、
私たちが紹介している本には、現場で大切にしてほしい考え方がたくさん詰まっています。
残り半年間、あらためて本を手に取ってみたり、日々の保育と照らし合わせながら理解を深めていただけたら嬉しいです。